アマプラに『プロミシング・ヤング・ウーマン』があったので観てみた。展開がどんどん予想しない方向にいくのでドキドキして面白かったけど、『リリイ・シュシュのすべて』にあったような宿命論の臭みを感じた。宿命論が社会正義と結びついて「コンテンツ」になることの危うさというか。

宇多丸氏がムービーウォッチメンで取り上げていたようなのでそれを聴いてみたところ、またしても「う〜ん」となってしまった(もっとも、わざわざ音声を聞かずとも書き起こしも公式に上がっているが、僕はわりと音で聴いてみている)。
シネマハスラー時代から彼の映画評はときどき聴いてるのだが、今は面白くないと感じることが多い。思うに、フェミニズムやポリティカル・コレクトネスなどのグローバル基準と目線を合わせようとしていることが大きい気がする。フェミニズムやポリティカル・コレクトネスが悪いものだとはまったく思わない。ところが、その潮流は少しのっぺりとしたものなので、そこに合わせようとすると自動的に批評性を失うのだと思う。
言い方は悪いかもしれないが、フェミニズムやポリティカル・コレクトネスを用いると、誰でも「批評的っぽいことが言える(ように思える)」。でもそれでは最早、一般ピープルと論理が同じになってしまうので、何かを批評しようとしても批評性が原理的に生じ得なくなってしまうのだと思う。もちろん、いわゆるフェミニスト批評の文脈で書かれた批評は面白い。だけどフェミニスト批評を表面だけ学んでもあまり意味はない感じがする。フェミニスト批評を書ける人は、生き様そのものからそれが生み出されているように思う。一朝一夕に真似できるものでもないなと。
『プロミシング・ヤング・ウーマン』に戻ると、物語の世界観が宿命論的だと感じた。フィクションがいつもサプリメントやエナジードリンクのようなものである必要はない。だけど、宿命論を美しいものとして作品の中で描き出すことに、僕は少し抵抗感を覚える。
何かの自己の関与をもって、ほんの少し自分の外側の世界に作用することがあってほしい。本作は、「思い知らせた」だけではあると思う。toxicな男性たち、彼らは「思い知る」ことにはなったのだろうけど、「思い知る」のと「変わる」のとは違うだろうと思う。「変わる」のには、考える・感じる主体が必要だ。本作のtoxicな男性たちにはそれがない。『プロミシング・ヤング・ウーマン』はテーマも展開も、演出も非常に素晴らしい。また、エンタメに寄り切らない姿勢もはっきりしていて良いと思う。だけど、「思い知る」ことと「変わる」ことの概念的な弁別がなされていないことは決定的に残念だと思う。それも、市場がそうさせているのだ。「思い知ればいい、変わらなくていい」という宿命論的な人間観によって、世の中が覆われていることを見せつけられてしまう作品でもあると思う。
(了)


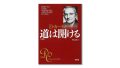
コメント