社会科学、政治、哲学などについて。
 社会
社会 ジャニーズ2度目の記者会見と望月記者
ジャニーズ2度目の記者会見をざっと見た。東京新聞の望月衣塑子記者は今ものすごく叩かれているようだが、個人的には少し応援している。前回記者会見では特に東山社長への被害経験の質問が問題となり、これに関しては他の識者・ジャーナリストが批判している...
 人類学
人類学 オックスフォードで筋トレに励む(谷憲一「人類学徒のオックスフォード研究日誌」第3回)
オックスフォードでは研究に励む日々ですが(たまに旅行もしています)、ジムにも毎日通っています。オックスフォードに来る前はほとんど自宅でトレーニングをしていました。その時は床に気を遣いながらゆっくりとバーベルを置いたり、少し軽めの重量でトレー...
 社会
社会 Podcast(44)ジャニーズ問題どう向き合う?“業界の片隅“から、メディアの責任を考える
Podcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。2023年3月のBBCドキュメンタリー放映以降、ますます拡大しているジャニーズ事務所前社長・ジャニー喜多川氏の性加害問題。メディアの責任を問う声も大きくなっていま...
 社会
社会 Podcast(43)『バービー』をめぐる消費環境の問題とは?『ストーリー・オブ・マイライフ』『セーラームーン』との対照から考える
Podcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。今回取り上げるのは、アメリカでは大ヒット作となった映画『バービー』。フェミニズム映画として批評されることの多い同作ですが、日米の“コレクトネス“への圧力や、『スト...
 社会
社会 Podcast(42)東大は奥多摩に移転すべき!? 日本の大学ヒエラルキーと秘密のハイ・ソサエティについて を更新しました(大学と地方創生、米軍基地についての追記あり)
Podcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。今回のテーマは「日本の大学ヒエラルキー」。なぜ東大は奥多摩に移転すべきなのか? そこにある階層化の問題、ハイ・ソサエティの「いやらしさ」、そして周辺環境について、...
 社会
社会 Podcast(30)密かに(いや、大っぴらに)日本を支配中?エリート男子校文化のヤバさを当事者目線で語る を公開しました
今日はもういっこお知らせですが、謎のPodcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。前回取り上げた『どうして男はそうなんだろうか会議』でも名指されていた、日本社会の意思決定権を握り続ける男性ホモソーシャル。この...
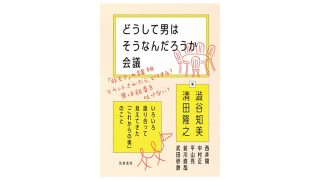 社会
社会 Podcast(29)『どうして男はそうなんだろうか会議』に関する会議〜男性論をめぐる語り口について〜 を公開しました(追記あり)
謎のPodcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。近年、社会的なイシューとしてますます重要性が高まっているジェンダーの問題。フェミニズム的な観点からの「男性論」も盛り上がりを見せています。2022年8月発売の...
 地理
地理 Podcast(28)2020年代の郊外論ことはじめ。なぜ「郊外」はあんなにバッシングされていたのか? を公開しました
謎のPodcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。90年代〜2010年代にかけて宮台真司『まぼろしの郊外』、三浦展『ファスト風土化する日本』、山内マリコ『ここは退屈迎えに来て』などをきっかけに流行していた〈批...
 社会
社会 意を決してBBCドキュメンタリー『J-POPの捕食者 秘められたスキャンダル』を観た
ジャニーズ事務所前社長である故・ジャニー喜多川氏の、所属タレントに対する性的虐待を取り上げたBBCのドキュメンタリー『J-POPの捕食者 秘められたスキャンダル』。公開されて以降、この問題が非常に話題になっている。僕も当然、この「疑惑」につ...
 人類学
人類学 谷憲一『服従と反抗のアーシューラー』セルフ解説④本書の射程と比較
これまでは、拙著『服従と反抗のアーシューラー』の対象であるアーシューラーの儀礼や、フィールドワークの経験についてセルフ解説を書いてきました。今回は本書の射程について、イランの宗教儀礼ついての情報を得るということを超えて、他の研究との比較を念...
 人類学
人類学 谷憲一『服従と反抗のアーシューラー』セルフ解説③儀礼の身体性をどう記述するか
前回はフィールドワークの中で胸叩き儀礼をおこなうヘイアトと出会った話について書きました。今回は拙著第二章「音文化の規制と儀礼の拡張」の内容にも少し触れつつ、フィールドワークの中で感じた身体感覚をどのように記述していくかということについて書い...
 人類学
人類学 カレッジの共食文化からオックスフォード大学を知る(谷憲一「人類学徒のオックスフォード研究日誌」第2回)
オックスフォード大学に来てから、自分にとって新鮮な概念の一つが「カレッジ」です。カレッジというと単科大学のことを思い浮かべることも多いかと思いますが、オックスフォード大学やケンブリッジ大学の場合には意味が異なっていて、まさにこれらの大学を特...
 歴史
歴史 Podcast(22)自衛官訓練=強制デジタルデトックス!? 知られざるその生活から「徴兵制」を考える を公開しました
謎のPodcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。これまでのPodcastの一覧はこちらから。小池、竹本、中野の20〜30代フリーランス編集者/ライター3名で、「この社会で働き生活する」ということについて、い...
 哲学
哲学 ターザンで『プリズナートレーニング』シリーズ翻訳者・山田雅久さんに取材しました。いま「身体」を考える意味とは?(セルフ解説つき)
ターザンで、『プリズナートレーニング』シリーズ全作、他にも関連書『ストリートワークアウト』など、フィットネス書籍の翻訳を多数手掛けている山田雅久さんに取材しました。バキの表紙でお馴染み! 日本の「囚人トレ」ブーム火付け役に、刑務所発の最新ト...
 人類学
人類学 谷憲一『服従と反抗のアーシューラー』セルフ解説②生活のなかで浮かび上がる問いを探求する
前回は、本のタイトルにもなっている「アーシューラー」とは何かについて解説しました。今回は、本書での研究がどのように遂行されたのかについて書いていきます。人類学的フィールドワークの特徴 文化人類学という学問の特徴の一つに長期間のフィールドワ...
 人類学
人類学 谷憲一『服従と反抗のアーシューラー』セルフ解説①そもそもアーシューラーとは何か?
いよいよ2023年4月に、法政大学出版局から私の初の単著『服従と反抗のアーシューラー』(法政大学出版局)が出版されます。本書は、2022年に一橋大学大学院社会学研究科に提出した博士論文を基に、改稿したものです。 毎年、法政大学出版局は「学術...
 社会
社会 Podcast(21)現代の重装歩兵とは? フリーランス編集者が予備自衛官補になってみた を公開しました(追記あり)
謎のPodcast「フリーランスが学ぶ!企業社会の歩き方」の最新回を公開しました。これまでのPodcastの一覧はこちらから。小池、竹本、中野の20〜30代フリーランス編集者/ライター3名で、「この社会で働き生活する」ということについて、い...
 人類学
人類学 オックスフォードに来ました(谷憲一「人類学徒のオックスフォード研究日誌」第1回)
ポスドクとしてオックスフォードに こんにちは。谷憲一です。こちらのブログで「人類学徒のテヘラン修行日記」を連載しておりました。その後、2022年2月に一橋大学より博士号が授与されました。いろいろあって2023年の2月から英国オックスフォード...
 歴史
歴史 国防婦人会と千人針カルチャー
最近、「文化系のための野球入門」を書く上での前提知識として必要なので、戦前の社会背景に関する勉強がちょこちょこと進んでいる。もっとも、連載で使えそうな記述はそっちに回すので、このブログで書いているのは「さすがにこのトピックは関係なさすぎるな...
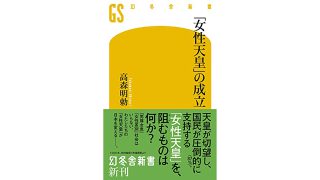 歴史
歴史 高森明勅『「女性天皇」の成立』、内館牧子『女はなぜ土俵にあがれないのか』を読んだ
連載「文化系のための野球入門」で、「伝統」というのものへの向き合い方、その進入角度についてヒントを得たく、高森明勅『「女性天皇」の成立』、内館牧子『女はなぜ土俵にあがれないのか』の2冊をざっと読んでみた。以下、備忘録である。高森明勅『「女性...